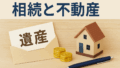相続において、遺言書(いごんしょ)があるかないかで、その後の手続きの流れやスムーズさが大きく変わってきます。
「遺言があると何が違うの?」「なかったらどうなるの?」という疑問に、やさしくお答えしていきます。
1. 遺言書とは?
遺言書とは、「自分が亡くなった後、財産を誰にどう分けてほしいか」を記した本人の意思を伝える文書です。
法的に有効な形式で書かれたものであれば、相続の内容は基本的に遺言通りに進められます。
2. 遺言書がある場合の流れ
もし遺言書が見つかったら、以下のような流れになります。
(1)まず「家庭裁判所での検認」が必要(自筆の遺言書の場合)
自筆で書かれた遺言書がある場合、勝手に開けてはいけません。
家庭裁判所に持って行き、「検認(けんにん)」という手続きが必要になります。
検認とは?
遺言書の内容を確認し、「この日、この形で存在していました」と記録するだけの手続きで、内容の有効性を判断するものではありません。
※ 公正証書で作成された遺言書なら、検認は不要です。
(2)遺言の内容どおりに分ける
検認が終われば、基本的に遺言に書かれている通りに財産を分けていきます。
「長男に家、長女に預金、三男にはなし」など、指定があればその通りに従います。
(3)遺言に従わないこともできる?
遺言があっても、相続人全員が合意すれば別の分け方も可能です。
たとえば「長女が現金をもらうことになっていたけど、家をもらいたい」といった希望がある場合、話し合いで変更することもできます。
3. 遺言書がない場合の流れ
一方、遺言書がないときは、「法律のルール」に従って財産を分けることになります。
(1)法定相続分での分割
法律では、それぞれの相続人に対して「何割もらえるか」が決められています(これを法定相続分といいます)。
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人なら、配偶者が1/2、子どもたちはそれぞれ1/4ずつです。
(2)話し合い(遺産分割協議)が必要
誰がどの財産を受け取るかを決めるため、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。
たとえば、「自宅は長男、預金は長女」といった具体的な割り振りを決める必要があります。
(3)全員の合意が必要
この話し合いは、相続人全員が同意しないと成立しません。
1人でも反対すると手続きが進まないため、トラブルが起きやすい場面でもあります。
4. よくある疑問と注意点
Q:遺言書に書かれていても、全財産を特定の人にあげられるの?
一部の相続人(配偶者や子ども)には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分が保証されています。
完全にゼロにされてしまった場合は、請求すれば一定の割合を取り戻せる可能性があります。
Q:遺言書が見つかったらどこに相談すればいい?
まずは弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
内容や形式が有効かどうかの確認も必要です。
5. まとめ
遺言書があると、手続きがスムーズに進むことが多く、相続人同士のトラブルも減らせます。
一方、遺言がない場合は法律のルールに従って相続人全員で話し合う必要があります。
「うちは遺言がないから不安…」という方も、まずは流れを理解することが第一歩です。
次回は、「相続財産には何があるの?」をテーマに、「何が相続の対象になるのか」「借金も引き継ぐのか?」といった気になる点を分かりやすく解説していきます。
どうぞお楽しみに!