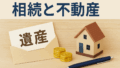申告が必要な人・必要ない人の違いとは?
「相続税って、誰でも払うの?」
「自分たちにも関係あるのか心配…」
そんな疑問を持っている方も多いかもしれません。
実は、相続税がかかる人は、全体のごく一部です。
とはいえ、「申告が必要なのに放っておいた」ということになると大変なので、
今回の記事では、相続税がかかるかどうかを判断するポイントを、やさしく解説します。
1. 相続税とは?
相続税とは、亡くなった方から財産を引き継いだときに、
一定額を超えた人に課せられる税金です。
引き継いだ財産の総額が、ある基準を超えない限り、相続税は発生しません。
2. 相続税がかかるかどうかの目安:「基礎控除」
相続税がかかるかどうかのカギは、**基礎控除(きそこうじょ)**です。
この金額までは税金がかからない、いわば「非課税のライン」です。
計算式は次のとおり:
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合:
3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円
つまり、相続財産の合計が4,800万円以下なら、相続税はかからないということになります。
3. 相続税がかかるかどうか、どう調べる?
まずは、財産の「総額」をおおまかに見積もってみましょう。
よくある財産の例:
- 預金(銀行口座など)
- 土地・建物などの不動産
- 株や投資信託
- 車や貴金属
- 生命保険金(一定額を超える部分)
これらを相続時点の時価で合計します。
「よく分からない」「土地の価値ってどう見るの?」という場合は、
税理士や不動産の専門家に査定してもらうと安心です。
4. 相続税の申告が必要なケース
財産の総額が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要です。
- 相続開始(亡くなった日)から10か月以内に税務署に申告
- 相続人全員の分をまとめて提出
- 税額が出れば、期限内に納税
遅れると延滞税や加算税がかかるので要注意です。
5. 「生命保険金」や「退職金」も要チェック
「保険金は非課税じゃないの?」と思う方もいるかもしれませんが、
正確には、一部が非課税です。
たとえば、生命保険金は
500万円 × 法定相続人の数までが非課税。
それを超える分は、相続財産として扱われます。
退職金も同様です。
6. 相続税の対象外になるケースも
以下のような制度を使えば、相続税の対象から外れる(または減額される)ことがあります。
- 配偶者控除:配偶者が受け取る財産は、最大1億6,000万円まで非課税
- 小規模宅地等の特例:住んでいた家や事業用の土地について、一定条件で評価額が下がる
- 未成年者控除、障害者控除などの個別控除もあり
こうした制度は、適用できるかどうかの判断が複雑なので、税理士への相談が安心です。
7. まとめ
相続税がかかる人は実は少数ですが、次のことをしっかり確認しておきましょう。
- 基礎控除の範囲内かどうかをまず計算
- 生命保険や退職金も含めて全体の財産を確認
- 10か月以内の申告が必要かどうか、早めに判断
「うちはかからないと思っていたけど、実は対象だった…」ということもあるので、
不安があれば専門家に相談してみてください。
次回は、**「専門家に頼むべき?自分でできる?相続手続きの進め方と費用感」**をテーマに、
司法書士・税理士・弁護士など、誰に何を頼むべきか、自分でやる場合との違いを詳しくお伝えします。
お楽しみに!