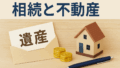相続手続きを始めるうえで、まず確認しなければならないのが「誰が相続人になるのか?」という点です。
法律で決められたルールがあるため、「長男だから全部もらえる」「同居していたから当然自分のもの」というわけにはいきません。
この回では、相続人になれる人の決まり方や、調べ方、そして家族の関係でよくあるパターンを、できるだけわかりやすく解説します。
1. 相続人とは?
相続人とは、亡くなった方(=被相続人)の財産を引き継ぐ権利をもつ人のことです。
誰が相続人になるかは、法律であらかじめ決められているので、本人たちの話し合いだけでは決められません。
2. 基本のルールを知ろう(法定相続人)
相続人になれる人には「優先順位」があります。以下が代表的な順番です:
【第一順位】子ども(実子、養子、認知した子を含む)
亡くなった方に子どもがいれば、配偶者と一緒に相続人になります。
配偶者は常に相続人になります。
【第二順位】父母(または祖父母)
子どもがいない場合、親が相続人になります。親もいないときは祖父母など、上の世代へとさかのぼります。
【第三順位】兄弟姉妹
子どもも親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
なお、すでに亡くなっている兄弟がいれば、その子ども(甥・姪)が代わって相続することもあります(代襲相続)。
【配偶者は必ず相続人】
上の順位に関係なく、配偶者(妻や夫)は必ず相続人になります。
ただし、内縁関係(籍を入れていない場合)では相続人にはなりません。
3. 相続人を調べるにはどうすればいい?
戸籍(こせき)を確認するのが基本です。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めることで、誰が相続人なのかがわかります。
どこで戸籍を取る?
- 本籍地のある市区町村役場で請求できます。
- 遠方の場合は、郵送でも取り寄せ可能です。
どんな書類が必要?
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 申請書(役所にあります)
- 手数料(1通450円程度)
4. よくある家族構成の例
以下は、相続人が誰になるのかをイメージしやすいよう、例をいくつか紹介します。
例1:夫が亡くなり、妻と子どもが2人
→ 相続人:妻、子ども2人(3人で分ける)
例2:独身の男性が亡くなり、親が存命
→ 相続人:父・母
例3:配偶者も子どももいないが、兄弟がいる
→ 相続人:兄弟姉妹
例4:子どもがすでに亡くなっていて、その孫がいる
→ 相続人:孫(子どもの代わりに相続できる=代襲相続)
5. 相続人の確認はトラブル防止にも
相続では「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、相続人を正しく把握していなかったためにトラブルになるケースが少なくありません。
「誰が相続人なのか」を明確にしておくことは、手続きをスムーズに進めるうえでとても大切です。
まとめ
相続手続きのスタート地点は「誰が相続人になるのか」を確認すること。
法律で順番や範囲が決まっているため、感覚で判断せず、戸籍をしっかり取り寄せて、正確に把握しましょう。
次回は、「遺言書がある場合・ない場合の違いって?」をテーマに、遺言の有無によって相続の流れがどう変わるのかをやさしく解説します。
遺言書は「あるだけで手続きがかなり変わる」重要なポイントですので、ぜひご覧ください。