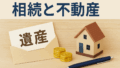相続が発生すると、「誰が、何を、どれだけ相続するか?」を話し合って決める必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」といいます。
今回は、遺産分割協議の基本的な流れや注意点を、できるだけわかりやすく説明します。
相続トラブルの多くがこの段階で起きるため、知っておくと安心です。
1. 遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、「相続人全員で、遺産の分け方を話し合って決めること」です。
遺言書がない場合、基本的に相続人全員の合意がないと遺産を分けることはできません。
例えば…
・家は長男が住むから長男がもらう
・預貯金は均等に分ける
・土地は売って現金で分ける
など、「誰が何を受け取るか」を具体的に決めていきます。
2. 話し合いに必要な人は?
話し合いには、「すべての法定相続人」が参加し、同意する必要があります。
参加が必要な人:
- 配偶者(夫・妻)
- 子ども(亡くなっている場合は孫などが代わりに相続)
- 兄弟姉妹(場合によっては)
※ 誰が相続人か分からない場合は、戸籍を取り寄せて確認しましょう。
3. 話し合いの内容と方法
話し合いの方法は、集まっても良いですし、電話や郵送でも可能です。
ただし、最終的には「遺産分割協議書」という書面にして残す必要があります。
協議書の内容にはこんなことを記載します:
- 相続人全員の名前と住所
- 誰がどの財産を相続するか
- 協議に全員が同意していること
この協議書に、全員が署名・押印(実印)し、印鑑証明書を添えます。
4. 遺産分割のパターンいろいろ
遺産の分け方には、いくつかのパターンがあります。
【現物分割】
財産そのものを分け合う
(例:家は長男、預金は次男)
【代償分割】
特定の人が財産をもらい、代わりに他の相続人にお金を払う
(例:長男が家をもらい、次男に現金で補償)
【換価分割】
財産を売って現金にし、それを分ける
(例:土地を売って兄弟で等分)
状況に応じて、もっとも納得できる方法を話し合って決めましょう。
5. もめたらどうなる?
相続人の中に反対する人がいると、話し合いはまとまりません。
そういった場合には、家庭裁判所で「調停」や「審判」を申し立てることになります。
ただ、裁判所での手続きは時間もお金もかかります。
できるだけ、冷静に話し合いで解決するのが理想です。
6. 協議書が必要な理由
「協議書なんて面倒」と思うかもしれませんが、これはとても大切です。
なぜなら、次のような手続きに使うからです。
- 銀行の口座解約・名義変更
- 不動産の名義変更(登記)
- 税務署への相続税申告
協議書がないと、手続きが進まないケースも多いので、しっかり作っておきましょう。
7. まとめ
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める大切なステップです。
スムーズに進めるためには、
- 相続人を確定する
- 財産をリストアップする
- 全員が納得できる分け方を探る
この3つがポイントになります。
「できれば争わずに済ませたい…」というのは誰もが同じ。
そのためにも、準備とコミュニケーションがカギとなります。
次回は、「相続人が複数いる場合、どう話し合えばいい?」というテーマで、具体的なケースや話し合いのコツ、もめないための工夫をご紹介します。
ぜひ次回もご覧ください!