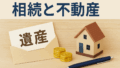「相続」と聞くと、家や預金など“財産をもらえる”イメージが強いかもしれません。
しかし実際には、プラスの財産だけでなく、借金やローンなど“マイナスの財産”も引き継ぐことになります。
今回は、「どんなものが相続財産になるのか?」をわかりやすく整理していきましょう。
これを知っておくことで、相続後のトラブルや思わぬ負担を避けることができます。
1. 相続財産ってどんなもの?
相続財産とは、亡くなった方(被相続人)が持っていた「お金に換えられる価値のあるもの」のことです。
大きく分けると次の2つがあります。
- プラスの財産:受け取って得になるもの
- マイナスの財産:支払う義務があるもの(借金など)
2. プラスの財産とは?
まずは、受け取ることができる「プラスの財産」から見ていきましょう。
主なプラス財産の例:
- 預貯金(銀行口座など)
- 不動産(土地・建物など)
- 株式・投資信託などの金融資産
- 自動車やバイク
- 貴金属や骨とう品
- 生命保険の「契約者が亡くなった方」であれば、解約返戻金
- 貸していたお金(貸付金)や売掛金
これらは、基本的に相続人に分けられる対象になります。
注意点:
生命保険金については「受取人が指定されている場合」、保険金はその人が直接受け取るため、相続財産には含まれません。
ただし、相続税の対象になる場合もあるので注意が必要です。
3. マイナスの財産とは?
つづいて、引き継がなければならない「マイナスの財産」を見てみましょう。
主なマイナス財産の例:
- 借金(銀行や消費者金融など)
- 住宅ローン(連帯保証人がいない場合)
- 未払いの税金や保険料
- 入院費・医療費の未払い分
- クレジットカードの残高
- 保証人としての債務責任
これらも相続の対象となるため、うっかり引き継いでしまうと、思いがけない借金を背負うことになりかねません。
4. その他、相続財産に該当しないものは?
すべてのものが相続財産になるわけではありません。
相続財産にならないものの例:
- 死亡保険金(受取人が指定されている場合)
- お墓や仏壇(祭祀財産といって、相続財産ではない)
- 個人の資格や地位(会社の役職など)
- 年金受給権(未支給分は例外あり)
これらは、原則として相続対象外です。
5. 相続放棄という選択肢もある
もし、「マイナスの財産の方が多そう」「借金を引き継ぎたくない」と思った場合、相続放棄という方法があります。
相続放棄とは?
相続が発生してから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てることで、一切の財産(プラスもマイナスも)を引き継がないとする手続きです。
注意点:
- 一度放棄すると撤回はできません
- 期限(3ヶ月)を過ぎると原則「相続を承認した」とみなされます
- 書類の準備や手続きはやや複雑なので、専門家に相談すると安心です
6. まとめ
相続する財産は、「得になるもの(プラス)」だけでなく、「支払いが発生するもの(マイナス)」も含まれていることが重要なポイントです。
内容をしっかり確認して、必要に応じて相続放棄や専門家への相談も検討しましょう。
次回は、「遺産をどう分ける?遺産分割協議ってなに?」というテーマで、相続人同士の話し合いの進め方や注意点をお伝えします。
「もめずに分ける」ためのヒントが満載ですので、ぜひご覧ください!